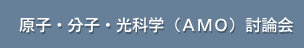
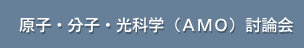 |
|||||
It has been naturally considered that few- and many-body systems can be accurately described by taking account of only two-body interactions among the constituents. In this session, we focus on recent hot topics related with three body forces by discussing examples from nuclear and atomic physics. From nuclear physics side, the importance and the challenges of three-nucleon forces for nuclear structure are introduced. Here, first as a discussion leader, Hiyama will review on the history of three-body force in nuclear physics.Three-body force generally plays important role in the binding energies in nuclei as well as nuclei with strangeness quark. One plays attractive role in the binding energies and the other plays in repulsive role in binding energies. However, still we have open question for desirable strengths of three-body forces. In this session, Hiyama will introduce also recent progress on three-body force.
Recently importance of three-body force has been pronounced in nuclear physics. Since Yukawa’s meson theory in 1935 the existence of three-body force acting among three-nucleons has been predicted. However, these forces are relatively small compared to two body forces and their effects are easily masked. Therefore, it is hard to find evidence for them experimentally. Study of the three-body forces has changed in the end of 1990’s. The following advances have made it possible to explore the three-body force effects in various nuclear phenomena. (i) Generation of the so-called realistic nucleon-nucleon forces (two-body forces). (ii) Achievements of ab-initio calculations based on the realistic nuclear forces. (iii) Development of experimental technique to obtain high precision data especially for the few-nucleon systems. I will review on the brief history and current topics of three-body forces in nuclei and the experimental approach to these forces.
Vitaly Efimov predicted in 1970 that resonant two-body forces between three particles
induce an effective scale-invariant three-body force that leads to the existence of three-body bound states, even in the absence of two-body bound state. Such states were originally predicted for nuclear systems, but were more clearly observed in atomic systems.
The spectrum of these states is characterized by only two effective parameters: the two-body scattering length between the particles, and a so-called three-body parameter, that depends on the details of the microscopic two-body and three-body forces.
I will show that in atomic systems even the three-body parameter is often determined by the
two-body forces only, due to the van der Waals tail of these forces, and I will discuss situations where three-body forces could play a role.
実験結果から統計的に対象の作用機序を推測する統計モデリングは、科学における重要な手法である。人工知能の分野では、深層学習に代表される統計的機械学習の技術が急速に進歩しているが、統計的機械学習の本質は、線形回帰や重回帰と同様、統計モデリングであり、そのため科学における新しい手法と捉えることができる。深層学習は特に、非常に高次元なパラメタ空間を扱うために、任意の非線形・高次元・不連続なモデルを近似することができ、生物や物性など今までモデル化が困難だった様々な現象に適用できると期待されている。
本セッションでは、レーザー加工における光と物質の複雑な相互作用のモデル化に深層学習を利用されている東大物性研の小林洋平先生、高次複雑系である光受容タンパク質分子の光化学的な分子物性のモデル化に統計的機械学習を利用されている同じく東大物性研の井上圭一先生にご講演いただき、科学における方法論としての統計的機械学習の可能性と課題を明らかにし、今後の科学の方法論の展望について議論したい。
画像認識において深層学習が他を凌駕したことを発端に近年機械学習の話題がにぎわいを見せている。様々な分野で機械学習の適用が進んでいるが数式で決定論的に表すことが困難な分野においてその威力を発揮している。我々はレーザー加工において適用が可能かどうかについて研究を進めている。
レーザー加工では,光や物質のパラメータが10-20 ある。光では波長、パルス幅、掃引速度や掃引パターン、フルーエンスや繰り返しなどがあり、物質には多数の物性パラメータがある。金属、半導体、誘電体では光の侵入、励起のされ方、エネルギー伝搬が大きく異なる。これら10-20次元の空間である目的-高品位加工や省エネ加工-のために最適なパラメータセットを産業界では解明したい。現在は職人が経験と勘でパラメータを導出している。
レーザー加工は、光が物質に照射されてから破壊に至るまでの物理プロセスがきわめて複雑であるため、学理構築には時間が掛かる。そこで、我々はパラメータを変化させて加工結果と紐づけた大量のデータをもとに機械学習を適用してパラメータを導出するという試みを進めている。
講演ではこのような取り組みと将来のサイバー空間を用いたものづくりについて議論をおこなう予定である。
ロドプシンは広範な生物種が持つビタミンAの誘導体であるレチナールを発色団色素として結合した、光受容型の膜タンパク質である。ロドプシンには動物の視覚に関わる動物型ロドプシンと、細菌などの微生物の細胞内でイオン輸送などの働きを光エネルギーをもとに行う微生物型ロドプシンの二種類が存在する。このうち微生物型ロドプシンは、近年光を用いて動物の神経活動を操作するオプトジェネティクス(光遺伝学)分野において、多くの研究に用いられている。興味深いことにこれらロドプシンは全て共通の発色団であるレチナールを用いているにも関わらず、420-600nmの幅 広い波長領域にわたって、分子ごとに異なる吸収波長を示す。これはレチナールとその周辺のアミノ酸との相互作用がタンパク質ごとに異なるためであると考えられている。しかしロドプシンは200-300残基のアミノ酸残基から構成され、それぞれの位置に20通りのアミノ酸が存在し得ることから、アミノ酸配列からその吸収波長を予想することは一般に困難である。そこで今回我々は過去に報告された微生物型ロドプシンの吸収波長についての研究と、独自に実施した実験結果をもとに、約800種類の分子についてアミノ酸配列と吸収波長のデータベースを作成し、それに対して機械学習法を適用することで新たな統計的モデルを構築した。その結果アミノ酸の一次配列のみから微生物型ロドプシンの吸収波長を±7.8nmの精度で予測できることが示された( Karasuyama and Inoue et al. Sci. Rep. (2018)15580)。またこのモデルは各残基がレチナールの吸収波長に与える影響を評価することができ、その結果これまでの研究では注目されていなかった2つの残基が吸収波長制御に関わることが明らかとなった。本手法はロドプシンの波長制御機構について多くの知見を与えるだけでなく、同様のアプローチによって他のタンパク質の機能に関わるアミノ酸の研究にもさらなる応用が期待され、講演では詳細な研究内容と共にこれらの展望を含めて議論する。
近年のレーザー技術の進展により、従来の周波数精度を大幅に凌駕する高分解能分光が可能になりつつある。1999年に開発された光周波数コムの技術は光周波数の精密な物差しとなり、15桁以上の周波数測定精度をテーブルトップの装置で実現している。また、2台の光周波数コム発生装置を組み合わせた時間領域分光法であるデュアルコム分光法は、光周波数コムを広帯域光源として用いる手法であり、高速かつ広帯域の精密分光を可能にした。光周波数コムの波長域は、非線形波長変換過程を通じて軟X線からテラヘルツ波長領域を網羅し、様々な波長領域での精密分光へ展開できる光源として注目されている。
一方、1980年代に発明されたチャープパルス増幅法(CPA)は、テーブルトップで高強度のフェムト秒パルスの発生を可能とした。CPA に基づくレーザー出力を用いて分子の振動回転周期よりも短い時間幅を有する数サイクルパルスを発生することで、分子の量子状態(回転、振動状態)の時間発展の実時間追跡が実現されている。特に、強レーザー場中で生成する親イオンまたはフラグメントイオンを観測量としたフーリエ変換分子分光では、分子イオンの振動数を従来手法と比べて精密に決定できることが報告されている。
本セッションでは、光周波数コムを用いた高分解能分光について佐々田博之先生(慶応義塾大学)に、強レーザー場を用いたフーリエ変換高分解能分光について安藤俊明先生(東京大学)に、最新の研究成果および研究動向についてご紹介いただく。スペクトル分解能が高いという特徴だけではなく、時間領域の計測と周波数領域の計測を相補する新規な高分解能分光手法への展開(例えば、高強度光周波数コムを用いた超高速分子ダイナミクス計測の可能性)について議論を行いたい。
1.はじめに
光周波数コムはよく周波数制御されたモードロックパルスレーザーで、これを使えば光周波数測定が革命的に簡便になり、大学の1研究室でも可能になった。我々は、分子スペクトルをサブドップラー分解能で記録し、その遷移周波数を、産業技術総合研究所計測標準部門と共同で製作した光周波数コムにより数kHz の不確かさで決定した。また、光周波数コムを広帯域光源として用い、高精度、高分解能、高速な分光測定を行った。
2.光周波数コムとサブドップラー分解能赤外分光
我々は2000年頃から周波数90THz(3000cm–1)付近で分子の振動バンドのサブドップラー分解能分光を行っていた。波長1.06μmのNd:YAGレーザーと波長1.5μmの外部共振器型半導体レーザーの光を導波路型PPLN に入射し、差周波発生光を用いた。幸運にも、これらのレーザー周波数は広帯域化したEr ファイバーコムの周波数範囲に入り、周波数測定ができた。
周波数86.7~ 93.1THz (2890~3100 cm–1)にあるCH4ν3バンドのサブドップラー分解
能スペクトルを観測し、P(12)~ R(8)の全許容遷移を含む204 本の遷移周波数を相対不確かさ約10–11で決定した。[1,2]この他に、H35Cl、H37Cl[3]、CH3D[4]、PH3[5]の精密遷移周波数測定、および、CH4のシュタルク効果の測定を行った。[6]
3.デュアルコム分光法
近年、光周波数コムを広帯域の光源として使う研究が急速に進んでいる。光周波数コムの利点を発揮するには1本1本のコムモードを分離して観測しなければならない。このためにデュアルコム分光法では、1台目の光周波数コムの出力光は試料を透過し、コムの各モードに吸収の情報を記録する。この光と、繰り返し周波数が僅かに異なる2台目の光周波数コムの光と重ね、ヘテロダインビートを観測して各スペクトル線毎に情報を読み出す。詳しい解説は拙文を読んで頂きたい。[7]
産総研では、二台のコムの相対線幅をHzレベルに狭め、これを用いてデュアルコム
分光を行い、分解能48MHzで波長1.0~1.9μmの広範囲を130msで測定できることを示した。[8]我々はアセチレン(12C2H2) 分子のν1+ν3バンドのスペクトル線幅の圧力依存性を調べた。2つの水素原子の核スピンが平行なオルソ(J”が奇数、スピン重率3)が反平行なパラ(J”が偶数、スピン重率1)に比べ圧力幅が大きいことがわかった。[9]これは今まで知られていなかった効果で、デュアルコム分光法がバンド全体のスペクトルをいっぺんに記録できるために初めて明らかになった。
4.おわりに
光周波数コムの使える波長領域を拡大する研究も世界的に大きく進展している。我々も導波路型PPLNによる波長変換を使って紫外から中赤外まで3.6オクターブにおよぶ光周波数コムを得ている。[10]また、光周波数コムの重要な応用例が数多く報告されている。
参考文献
1) S. Okubo et. al., Opt. Express, 19, 23878-23888 (2011).
2) M. Abe, K. Iwakuni, S. Okubo, H. Sasada, J. Opt. Soc. Am. B 30, 1027-1035 (2013).
3) K. Iwakuni, H. Sera, M. Abe, H. Sasada, J. Mol. Spectrosc. 306, 19-25 (2014).
4) M. Abe, H. Sera, H. Sasada, J. Mol. Spectrosc. 312, 90-96 (2015).
5) S. Okuda, H. Sasada, J. Mol. Spectrosc. 346, 27-31 (2018).
6) S. Okuda, H. Sasada, J. Opt. Soc. Am. B 34, 2558-2568 (2017).
7) 佐々田 博之、「分光研究で用いられる光コム」、分光研究、62, 99 (2013).
8) S. Okubo et. al., Appl. Phys. Express, 8, 082402 (2015).
9) K. Iwakuni et. al., Phys. Rev. Lett. 117, 143902 (2016).
10) K. Iwakuni et. al., Opt. Lett. 41, 3980-3983 (2016).
近年の超短パルスレーザー技術の発展に伴い、可視近赤外領域において高強度・サブ10フェムト秒パルスの発生が可能となった。これらの光源を用いたポンプ・プローブ計測によって、分子の振動・回転を実時間領域で観測することができる。また、生成したイオンの収量を遅延時間に対してフーリエ変換することによって、分子の回転振動スペクトルを得ることできる。我々は、この分光手法(強レーザー場フーリエ変換高分解能分光)によって、水素分子イオンの振動回転スペクトルを得た。
中空ファイバーを用いたパルス圧縮法によって、チタンサファイアCPAレーザーの出
力(0.5mJ,30fs)から、数サイクル高強度レーザーパルス(0.2mJ,5fs)を発生させた。得られた数サイクルパルスを用いて水素分子(D2)のポンプ・プローブ計測を行い、得られた親イオンとフラグメントイオンの収量を、遅延時間(0.3~527ps)に対してフーリエ変換し、D2, D2+の振動回転スペクトルを得た。
得られた振動回転スペクトルから、D2分子、D2+分子ともに10-4cm-1の不確かさ(相対不確かさ: 10-7)で振動数が決定できることが明らかとなった。D2分子の振動数の不確かさは、REMPIを用いた先行研究と同程度であり、D2+分子の振動数の不確かさは、光電子分光による先行研究よりも2桁低いものとなった。掃引する遅延時間の範囲を広げれば、周波数分解能をさらに向上させることが可能である。
細胞内にある液-液相分離がいま注目を集めている。たとえば抗体とポリアミノ酸や、構造をもたない天然変性タンパク質とRNA などを混合すると、組み合わせによっては白濁するが、この状態をつぶさに観察すると球状をしたドロプレット(液滴・濃縮体)が見える。このありふれたドロプレットが、細胞内ではDNAの修復や、遺伝子の転写、タンパク質への翻訳、シグナル伝達の制御、自然免疫の応答、機能の区画化や基質の貯蔵、外部環境からのストレスへの応答、アミロイドへの成熟などにかかわっていることが、次々に発見されてきている。また、分子や構造、会合などのこれまでのタンパク質の見方だけでは理解しにくかった現象、たとえば、翻訳後修飾のようにごくわずかな化学修飾がなぜ細胞内に高次の応答を引き起こすのか、なぜ危険なプリオンが種をこえて存在しているのか、固有の構造をもたない領域をもった天然変性タンパク質がなぜこれだけたくさん存在するのか、代謝の連続的な反応はなぜ起こるのか、このような問いには、「相分離メガネ」をかけると答えることができる。
ドロプレットは熱力学的に安定化されているだけで、界面には脂質膜などの仕切りはない。そのため分子は自由に出入りしている。またドロプレットは、生体分子の濃度が異なるふたつの溶液が分離しているだけなので、わずかな温度やpH やイオン強度の変化や、ATPやRNAや代謝産物のような低分子などの存在で、形成したり溶解したりする。これまで生命の現象は、分子と構造から理解が深まってきたが、これからは液-液相分離をはじめとした集合状態から理解する時代がはじまっている。今回の講演会では、この分野の萌芽期にきわめて重要な発見をした森英一朗博士と吉澤拓也博士
とともに、「相分離生物学」と呼べる新しい分野の可能性を議論したい。
タンパク質構造を持たない天然変性配列はlow-complexity( LC)ドメインとも呼ばれており、様々な疾患との関連性が指摘されている。細胞の中には、膜を持たないオルガネラ( membrane-less organelle )が存在しており、その形成には液- 液相分離( liquid-liquid phase separation:LLPS)という現象が重要であるということが徐々に明らかになってきた。米国テキサス大学Southwestern Medical CenterのSteven L. McKnightらは、LLPSの分子基盤の1つとして、LCドメインによるcross-βポリマー形成が重要であることを明らかにしてきた[Kato M, et al. Cell 2012; Han T, et al. Cell 2012; Kwon I, et al. Cell 2013; Kwon I, et al. Science 2014; Xiang S, et al. Cell 2015; Murray DT, et al. Cell 2017; Murray DT, et al. PNAS 2018; Kato M, et al. Cell 2019]。
発表者は、この一連の研究の中で、Steven L. McKnight らと共に、LC ドメインのcross-βポリマー形成の破綻と疾患との関連について明らかにしてきた[Lin Y, Mori E, et al. Cell 2016; Shi KY, Mori E, et al. PNAS 2017]。本演題では、McKnightラボの初期の発見から今日に至るまでの経緯を踏まえて、LC ドメインのcross-βポリマー形成によるLLPSの機序とその生物学的意義について紹介したい。
生体高分子の液-液相分離(liquid-liquid phase separation:LLPS)は、細胞内における膜の無いオルガネラの形成機構として注目を集めている。細胞が液-液相分離を利用するメリットとして、周囲の状況に応じて柔軟にすばやく、集合体の形成と消失を行える点がある。この液-液相分離の始動および制御は非常に繊細であり、様々な因子が関与することが明らかとなってきている。
本演題では、近年の液-液相分離研究のモデルタンパク質ともいえるFUSとその制御因子について紹介したい。FUS は526アミノ酸残基から成るRNA 結合タンパク質であり、細胞内においてはRNA 顆粒などの液-液相分離を主導すると考えられている。大部分がlow-complexityドメインと呼ばれる特徴的なアミノ酸組成から成る繰り返し
配列であり、この領域は単独では構造を持たないが、液-液相分離によるドロップレットおよびポリマーの形成に大きく寄与することが明らかとなっている。FUS の液-液相分離はアミノ酸組成以外にも、様々な要因による影響の研究が進められている。リン酸化、メチル化などの翻訳語修飾、RNA、低分子、温度、塩などが、FUSの液-液相分離を促進あるいは抑制し、物性を変化させるこが報告されている。以上のようなこれまでに報告されている研究成果と、発表者が行ったFUSの相分離シャペロン研究を具体例として紹介する (Yoshizawa et al., Cell 173(3) 693, 2018) 。相分離生物学を通すことで初めて見えてきた液-液相分離性タンパク質の分子動態に迫りたい。
多くの単位の定義は科学技術の進歩とともに進化し、より普遍的な定義へと変遷してきたが、キログラムだけは1889年に国際キログラム原器(IPK)によって定義されて以来、人工物に頼る最後のSI 基本単位として残っていた。この単位をプランク定数やアボガドロ定数によって再定義するための研究が1970年代から行われてきたが、従来はIPKの質量安定性を超える精度でこれらの定数を測ることがこれまではできなかったため、キログラムの定義改定は長い間実現しなかった。21世紀に入ってからようやくキッブルバランス法やX線結晶密度法によってこれらの定数を高い精度で測定することが可能になり、2018年11月にメートル条約にもとづいて開催された国際度量衡総会においてキログラム、アンペア、ケルビン、モルの定義をそれぞれプランク定数、電気素量、ボルツマン定数、アボガドロ定数によって同時に改定することが採択され、2018年5月20日(世界計量記念日)から新しい定義が施行された。これによってSIは人工物などに頼らない理想的な単位系へと進化した。本セッションでは特にキログラム、アンペア、ケルビンの新しい定義と、それらがもたらす新しい計測技術について展望する。
1) 藤井賢一: プランク定数を決める! ― キログラムの定義改定へ― , 応用物理, 87,
774-779 (2018)
2) 藤井賢一, 島岡博一: 進化する単位― 物理定数にもとづくキログラムとモルの新
しい定義―, 現代化学, 576, 29-36 (2019)
アンペアは7つの基本単位のうち唯一電気関係量の単位である。従来は磁気定数μ0(真空の透磁率)を定義することで定められていた。しかしこの定義では産業界の要求を満たす計測が不可能であったため、電気標準全体が、実態としてはジョセフソン定数2e/hとフォン・クリッツィング定数h/e2を「暫定的に定義値」(この値を協定値と呼ぶ)とし、それぞれによる電圧、抵抗標準を起点とすることで運用されてきた。つまり純粋な意味ではSIトレーサビリティを失っている状況であった。改定SIでは、電気素量eと並びプランク定数hも定義定数となるため、ジョセフソン定数とフォン・クリッツィング定数も同時に定義できることとなる。つまり「暫定運用」されていた電気関係量の標準が、完全に力学量と調和してSI全体でトレーサビリティを体系作ることになる。今回は、以上の歴史的背景と、改定SIに忠実な電流の発生、計測手法やその応用について解説したい。
国際単位系SIの7つの基本単位の一つである、熱力学温度の単位ケルビンKは、これまでは水の三重点により定義されていた。これに対し、改定後のSIにおいては、ケルビンKは今回新たに物理定数として定義されたボルツマン定数kに基づいて定義されることとなった。本講演では、国際単位系SIの制定から今回のSIの定義改定に至る温度の定義の変遷について紹介する。今回のSIの定義改定においてボルツマン定数kの決定に関わった幾つかの熱力学温度測定法について解説する。最後に、精密温度計測における今後の方向性や、新しい温度測定技術についても簡単に紹介したい。